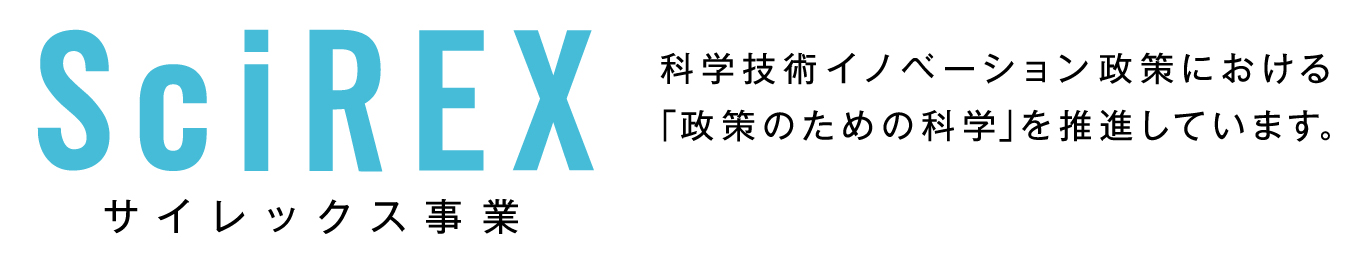SciREXオープンフォーラム2022 シリーズ第3回
持続可能な社会システム実現のための
SciREXオープンフォーラム2022 シリーズ第3回
持続可能な社会システム実現のための
科学技術イノベーション政策をどう設計していくか
〜アフターコロナ時代に向けて〜
大学経営マネジメントの取り組み−江端氏
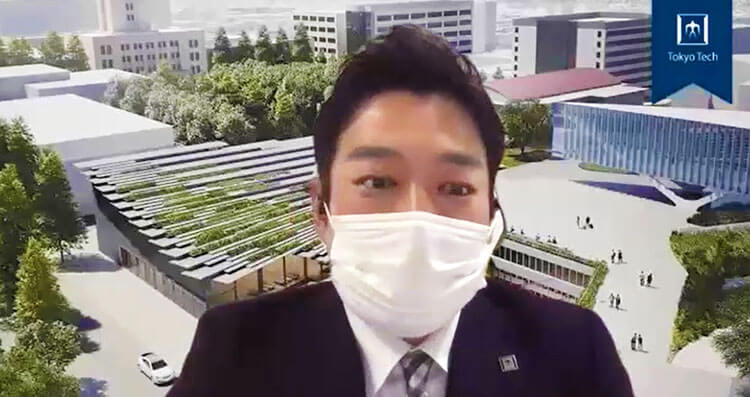
江端氏は、大学経営、マネジメントについての取り組みを紹介しました。東京工業大学は、学長による部局長指名、人事委員会の設置等の経営改革を行ってきました。特筆すべきは、プロボスト(総括理事、学長が学外との関係を構築するのに対し、プロボストは学内運営に責任をもつ)制度を活用し、独立した経営を進めている点です。
江端氏は、現在の大学経営が抱える課題として、投資効果とコスト分析に基づく大学経営、優れた人材養成の場の形成、研究成果を社会に還元するシステムの構築を挙げました。これら課題解決のために、東京工業大学では、URAとは別にマネジメント専門の戦略的経営オフィスを開設しました。また、技術職員上位職をつくり研究環境を整備する人材を養成。90名の技術職員が活躍するオープンファシリティセンターを開設し、産学連携の窓口としています。また、技術者養成制度(東工大TCカレッジ)を2021年に立ち上げ、産業界も含め全国規模で人材の養成を始めました。加えて、スタートアップ支援やアントレプレナー教育にも力を入れています。
江端氏は、「大学等における研究設備・機器の共用化のためのガイドライン等の策定に関する検討会」の座長も務めています。その立場から、内閣府がEBPM(Evidence-based policy making証拠に基づく政策立案)を推進するために設けたe-CSTI(STI関連データを収集し、データ分析機能を提供するシステム)を用いて、研究設備・機器の共用状況を調査した結果を紹介しました。国立大学資産の共用は全体では17%程度と低い一方、政策の採択校で重点支援を受けた地域貢献型大学では、共用化率が高いという傾向も見られ、政策的効果があったと評価しました。今後は、単なる共用状況だけでなく、研究・教育効果を測れるような指標も整備しながら、エビデンスに基づき制度改革に取り組みたいという考えです。
パネルディスカッション 「STI政策はいかにあるべきか」

パネルディスカッションにはコメンテーターとして政策立案や調査研究に携わっている文部科学省科学技術・学術政策研究所(NISTEP)上席フェローの赤池伸一氏も加わりました。
黒田氏からの「無形固定資産(ナレッジ)とは何か」という問いかけに冨山氏は「Apple のジョブズはデバイスに音楽配信iTunesを繋げれば大きな価値を産むと気づいた。何かを重点的に推進する計画経済的思考ではなく、彼のような、研究開発を担う知的プロフェッショナルを支援すべきだろう。そのため、社会課題解決をするメガベンチャーの始まりに関与する人たちが自由闊達に交流できるような日本の社会システムが必要になる。世界トップレベルの科学技術プラットフォームがあり安心安全な社会をもつ日本は、世界でも稀有な魅力的な国だ。世界中の知的プロフェッショナルを日本に呼べる可能性がある」と述べました。
黒田氏が「メインエンジン」となる大学の役割について「私智私徳を公智公徳にするのは学者の役割」という福沢諭吉の言、「私的なナレッジを社会のウィズダムにするにはインテリジェンスが必要」という丸山眞男の言を紹介すると、冨山氏も、「高度人材は社会的共通資本。そして、人材は流動化しているので、人への投資効果を測る際に人的資本が大学内で生み出す価値だけでなく、広いネットワークで生み出した価値を評価すべき。たとえば、MITに引き抜かれるような人材を育て、また戻ってきてくれるようにすればよい」と続けました。池内氏は、「流動する人材や、施設の共用化により生み出されるネットワークはまさに『無形資産』である」と指摘しました。これを受け江端氏は「大学が輩出した人材が社会のエンジンとして、どのような価値を生み出したかを評価し、社会に実感してもらえる方法を探りたい」と述べました。
冨山氏は、卒業生の寄付から研究資金やスタジアム建設資金を得ているスタンフォード大学を紹介し「大学がエコシステムの中心となっている。パスツール象限の研究成果がいずれ基礎研究の充実にも還ってくる。日本の大学もエコシステムの中心となるポテンシャルを十分に持っている」と評しました。
坂本氏は大学がナレッジから新しい価値を生み出すエンジンとなるために、「人的資本を拡充し、大学が経営体に進化することが重要」と強調しました。江端氏は「施設・設備関連の財務管理を経営判断に使えるフォーマットに整備するのが早急の課題」と現場の実態を紹介しました。赤池氏は、有形固定資産よりも人材などソフトパワーの資産を可視化しEBPMにつなげるという新たな取り組みも必要だと付け加えました。
最後に赤池氏は「これまで『成長と科学技術』についての議論が多くなされてきたが、今後、『分配と科学技術』の議論も加えるべき」という気づきを紹介し、「一過性の分配ではなく、長期的な視点で価値を分配できる方法が必要だ」と強調しました。そして、STIをめぐる現象を見える化するSciREX事業「科学技術・イノベーション政策の経済社会効果分析の政策形成プロセスへの実装」を紹介し、会を締め括りました。
登壇者

パネリスト
科学技術振興機構・研究開発戦略センター 特任フェロー /
慶応義塾大學 名誉教授
黒田 昌裕(くろだ まさひろ)

パネリスト
株式会社経営共創基盤 IGPIグループ会長
冨山 和彦(とやま かずひこ)

パネリスト
文部科学省大臣官房審議官(研究振興局及び高等教育政策連携担当)
坂本 修一(さかもと しゅういち)
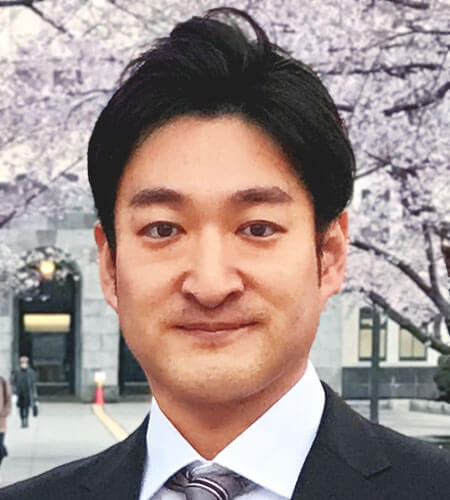
パネリスト
国立大学法人東京工業大学戦略的経営オフィス 教授
江端 新吾(えばた しんご)

コメンテーター
文部科学省科学技術・学術政策研究所 上席フェロー
赤池 伸一(あかいけ しんいち)
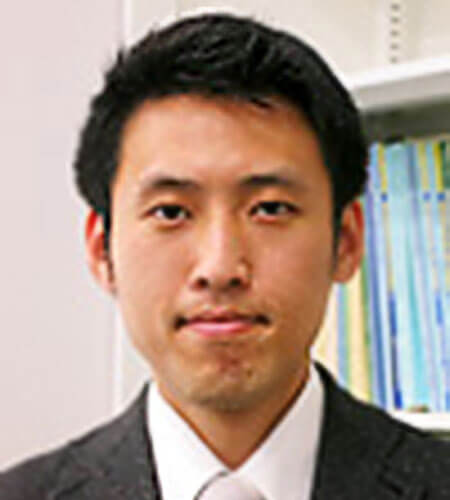
モデレーター
政策研究大学院大学SciREXセンター 特任フェロー /
独立行政法人経済産業研究所 上席研究員(政策エコノミスト)
池内 健太(いけうち けんた)
※所属は開催当時のものです