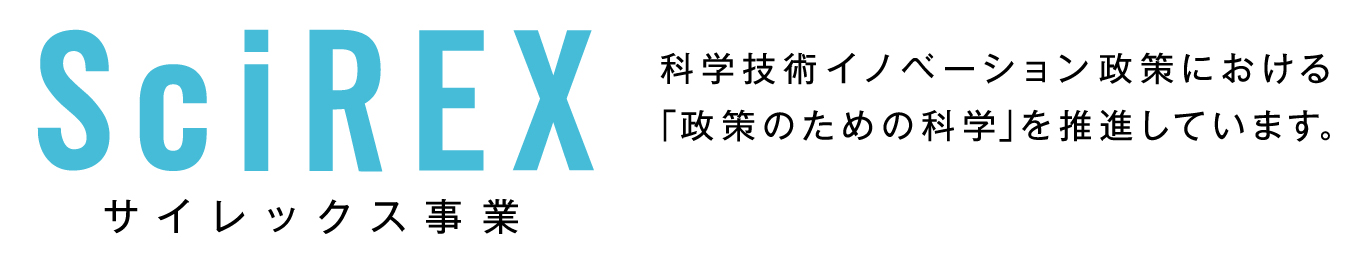SciREX オープンフォーラム2022 シリーズ第4回
研究力強化への処方箋を
SciREX オープンフォーラム2022 シリーズ第4回
研究力強化への処方箋を
実効性あるものとするために
システム・エンジニアリングの活用を
続いては、 JST社会技術研究開発センター「科学技術イノベーション政策のための科学 研究開発プログラム」で実施する研究プロジェクトの取り組みをもとにした報告です。発表者の小泉周氏は、研究力強化を目的とした若手研究者への支援などの施策が部分最適化に留まっている可能性を指摘します。全体最適化を考えるのであれば、シニア研究者を対象とする施策も含め、各施策の相関や関係性を把握し、好循環や悪循環を見極めたほうがいい。その手段として「因果ループ図」のようなシステム・エンジニアリングの手法を取り入れてはどうか——という提案です。

さらに小泉周氏は、基礎研究の成果を社会インパクトからバックキャストで評価することの危険性を指摘しました。バックキャストで社会的インパクトと基礎研究の成果の間に相関があるというエビデンスがあったとしても、それは、必ずしも「この基礎研究に投資したら社会的インパクトが生まれる」という因果関係を示すものではないといいます。基礎研究が社会インパクトを生んだかで評価するのではなく、むしろ、基礎研究に、その先の応用開発研究の間に横たわる「川」を乗り越えられるだけの「厚み」——論文などのナレッジの蓄積、研究の多様性、異分野・異セクターへのナレッジの広がり、アジャイルな研究活動の展開など——があるかどうかで評価してはどうかと提言し、報告を締めくくりました。
どうすれば日本の研究力を強化できるのか
以上の報告者4名をパネリストに迎えたディスカッションでは、まず、第6期基本計画のさまざまな政策群が実行されている中で行政府に何を提言できるか、そもそも「研究力低下」という問題設定自体が正しいかという論点をめぐって議論が交わされました。

長根氏は「博士人材に関連したキャリアパスの拡大や処遇改善の施策はよい方向に向かっている」として、有給インターン制度を取り入れ、国内外から優秀な学生を集めている沖縄科学技術大学院大学(OIST)の例を挙げました。さらに研究力を全体最適化するのであれば、若手だけでなくシニアの処遇も検討すべきだとし、「アクティブに研究業績を出し、外部資金も取って来られるような大学教員を定年など年齢で切る必要はない。頑張りに応じて先が拓ける道を示さないかぎり若手もついてこないだろう」と述べました。
若手研究者の支援については、小泉周氏が「研究の厚みを評価すべき」という発表を補足して「若手の多様性が育つよう評価すべきである」と述べました。それに対し、林氏から「厚みを増やすことと、限られた資源の中での研究の効率性をどう両立するか」という参加者の声をまとめた質問があり、小泉周氏からは「設備共用を柔軟に運用して若手が大きな資金を得なくても必要な装置を使えるようにするなど、国が基盤的な支援のための施策を積み重ねることが重要」と応じました。
議論を通じて浮上してきたのは「研究力強化をめぐる日本の方針」というもう一つの論点です。福本氏は「国としてどのような研究や研究者を支援したいかがぼやけている」と指摘しました。小泉秀人氏も「ミッション志向型の研究は、例えば特許の数を最大化するといった具体的な目標がある場合には有効な手立てとなるが、どこにどれだけの資金を投入するかの方向性、優先順位といった全体的なデザインをしっかりする必要がある」とし、分野間、研究のフェーズ間での分配の根拠となるエビデンスを提示できるような政策研究が求められていると述べました。
また、研究のみならずエビデンス・ベーストな政策立案でも重要であるとされたのが「データ」の問題です。小泉秀人氏は「欧米では国のデータが入手しやすく、それだけで影響力のある研究ができるが、日本ではそれができない。時折ニュースとなる国の統計のミスなども、研究者がチェックに関われば起こりにくくなる」として、国と研究者が協力してデータベースの構築を行うことが研究とEBPMの両方を推進する手立てとなりうると示唆しました。
モデレーターの林氏は「日本の研究力強化の目的をどう設定するのかは、政策研究者にとっても行政側にとってもチャレンジングな課題だが、研究者としては、データ分析に加え、制度などの質的な側面、歴史的視点などから多面的な研究を行い、行政と協力しながら取り組んでいく必要がある」とまとめ、ディスカッションを締めくくりました。
登壇者

パネリスト
千葉大学 大学院社会科学研究院 教授
長根(齋藤) 裕美(ながね ひろみ)

パネリスト
広島大学 大学院人間社会科学研究科 特任助教
福本 江利子(ふくもと えりこ)

パネリスト
自然科学研究機構 特任教授
小泉 周(こいずみ あまね)

パネリスト
一橋大学 イノベーション研究センター 特任講師
小泉 秀人(こいずみ ひでと)

モデレーター
政策研究大学院大学 教授 / SciREXセンター長代理 /
GiSTプログラム ディレクター
林 隆之(はやし たかゆき)
※所属は開催当時のものです