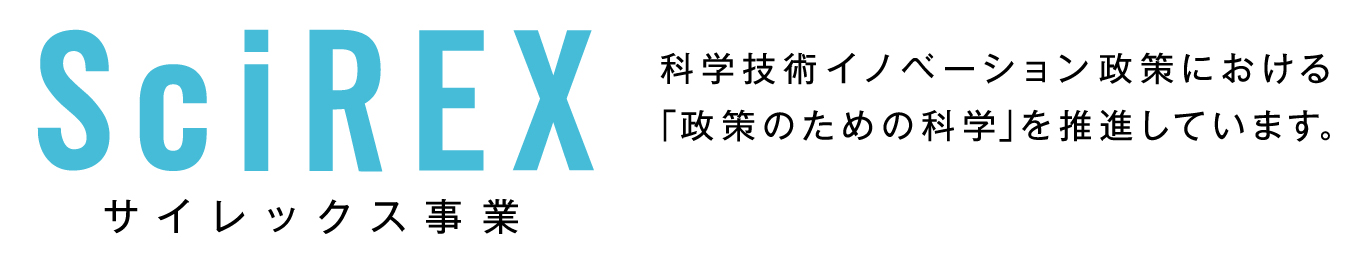第50回SciREXセミナー
開催報告⾰新と成⻑の源、
第50回SciREXセミナー
開催報告⾰新と成⻑の源、
⽇本における研究インフラの
エコシステム形成
エコシステムを介して⽣じる作⽤の戦略的マネジメント
続いて隅藏⽒は、「研究インフラのエコシステム構築においては、技術者による⾼度サービスと利⽤研究者の間で循環がある。そして、プラットフォームが重要。技術者のキャリアパスや、雇⽤の安定化といった観点もある」と確認し、このプラットフォームをどこが担うのかといった今後の実装に向けた課題を問いました。
これに対して永野⽒は、「さまざまな⾒⽅があっていいが、どこか1カ所だけでといった話をしだすとおかしくなる。⽇本の研究は世界とつながっていく必要があり、⽇本全体で研究機関のリソースを考えたときに、バーチャルにつながるかたちでもよい」と答えました。
また、プラットフォームの持続可能な成⻑要件として、下記の2点を挙げます。
- ①プラットフォームを介して存在する⼈々が継続的に増加する仕組みを持つこと
- ②プラットフォーム上の情報(研究データや新しい研究課題、研究ニーズ等)が継続的に増え続けるような仕組みとしてデザインしていること
「このどちらか、もしくは両⽅⽋ける状態だとプラットフォームが機能しなくなる」と説明しました。
これを受けて熊本⽒は、⾃⾝がサポート役として携わったナノテクノロジープラットフォームでの経験を踏まえ、最新装置の導⼊が⼈材集積の要因となり、新技術開発と⼈材育成の好循環を⽣み出した事例を紹介。また、共⽤の場でのイノベーションが機器開発を促進し、さらなる共⽤へとつながる循環の重要性を強調しました。さらに、2000年頃にドイツのベンチャー企業により開発された電⼦顕微鏡技術でゲームチェンジが起こった例を⽰し、 「研究インフラが整備されていく中で⽇本企業も⾃社での開発が進み、世界最⾼性能のものを作るようになった」と振り返ります。開発の循環について、「共⽤の場を使うことでイノベーションが起こり、それによって機器の開発が進み⾼度化が進む。⾼度化したものがまた共⽤に置かれるというサイクルが起こってくると、プラットフォームが機能する」と説明しました。
これに対して永野⽒は、「エコシステムのイメージは、アマゾンのジャングルのような熱帯⾬林。⼈が織りなすエコシステムでは、循環させるテクノロジーやノウハウ、知識、研究開発課題によってエコシステムに進化を起こすことが重要」と述べ、エコシステムとして⻑期的な設計の重要性を強調しました。

参加者からは、以下のような質問が出されました。
質疑1:研究機器を海外に頼ることの課題として、調達価格の上昇や導⼊の遅れ、そしてそれに伴う研究の遅れが指摘されるが、これの具体的なデータはあるか。
永野:個々にいくつかの先端機器を⾒ていると、おしなべて過去10年間で、⽇本で調達するときの価格は2倍から、⾼いものは3倍ぐらいまで価格が上がっている。⼀⽅、使える資⾦が2倍、3倍になっているわけではないため、実際は調達のボリュームは減り、新技術への更新は滞っている。
質疑2:これらを含めた多様な課題(産業としてマーケットが取れていないことも含む)に鑑みた場合に、政策として⽬指すゴール・指標に考えはあるか。
永野:産業政策の観点で考えたときには、こういった機器や分析、あるいは加⼯、その産業界全体の発展をどう捉えるかになってくる。装置によって解明したり加⼯できたりといった産業を持つことは、⽇本にとって⽣命線ではないか。⼀⽅、科学技術政策の観点から考えたときには、⽇本の研究⼒のベースラインを上げながら先端部分をどこでキープしていくのかになってくる。 これらは両⽅あり、産業政策と科学技術政策の接続を考えたときに、本来の意味でのイノベーション政策論になる。両者を分離させずに、イノベーション政策としての相乗効果で考えるべきではないか。
質疑3:⽇本では従来から共同利⽤拠点や⼤学共同利⽤機関が、コミュニティーの要望に応えて機器の整備を⾏う役割を持っている。近年の研究基盤の「共⽤」の議論は、これらのボトムアップ型の「共同利⽤」制度とは分けて語られている印象があるが、戦略的なイノベーション調達の制度設計において、ボトムアップ型の「共同利⽤」の役割はどのようなものになるか。
永野:例えば国が公的資⾦を投じ、JSTのプログラムで研究開発を⾏ったテクノロジーなどでも、プロジェクト期間が終わったときにその技術開発が⽌まってしまうことがある。そこを⽌めずに実装して利⽤にまでこぎ着けるのがイノベーション調達の海外のスキーム。途中まで開発が進んできたイノベーションの種・芽を、いかにイノベーションの成果として獲得するのかに⼒点がある。 開発技術の現場利⽤が拡がって成果を⽣み出すことが本来の⽬的であり、他国よりも早くイノベーション成果を獲得するためのプログラムになっている。それを担う組織が共同利⽤・共同研究拠点であってもいいかもしれないし、政策的に資源を集中させた研究拠点のような場にあってもいいのではないか。
質疑4:「イノベーション調達制度」をWTO政府調達協定と整合的に運⽤するための⼯夫としてどのような要素が重要になるか。⽶欧の⾏政府はどのように整理しているのか。
永野:製品上市前の段階で、研究開発を含む調達だとして線引き・整理をすることによって、欧州委員会および欧州加盟国、韓国、⽶国においても、いずれもWTO協定の政府調達の対象外として取り扱っている。
質疑5:JSTの戦略的創造研究推進事業などの政策と、こういったインフラを整備していくような共⽤や機器開発は⼀緒になるのか、別物なのか。
永野:拠点政策やインフラに関わる政策と、ファンディングによる研究プログラム・プロジェクトは、それぞれにミッションがある。異なる⼈がそれぞれの現場を担っていたり、異なる⼈が制度設計をしていたりする。しかし、現場を少し広げてみると、実はその⼈たちは同じ敷地や同じ建物にいたりする。つまり、皆隣り合っているぐらいの感覚で施策の関係性を組むことが本当はできるはず。
⾃⾝がやっている施策であったり、⾃⾝が参画しているプロジェクトだけの限られた範囲のことだと切りとって考えてしまった途端にギャップが⽣まれてくるので、そこはちゃんと両⽅ともが相互に作⽤しあうものだとの認識を持つことが重要。研究開発のエコシステムは、誰か1⼈が全部を仕切れるわけではない。だからこそさまざまな⽴場の⼈たちが、恒常性や変容性みたいなものを持ち合わせながらエコシステムを進歩・進化させていくことに合意が要る。中での役割分担や接続ポイントは、⼀定の重なりや冗⻑性を認めるようにしていくことも求められるだろう。
質疑6:話の(中に)あった「未知のサイエンス」に対して、今はないテクノロジーで取り組んでいくといったときに、連続的な研究機器の進歩ではないところになるのでは。すなわち、解像度が今までこのぐらいだったものが1桁上がるなどは連続的なもの。そこを狙っているのか。もう⼀歩先に⾏くと、そもそも新しい原理の開発のようなことを⾔っているのか。その辺りのイメージがあるとユーザーと開発者、それから共⽤の三つの機能がつながっていると新しいものができるとのイメージが持ててワクワクするのではないか。
永野:インクリメンタルなものなのか、ディスラプティブなものなのかということだと思う。実はその境界は結構曖昧。例えば、NMRの⾼磁場化などは⼀⾒インクリメンタルに思えるかもしれない、400メガのNMRが800メガ、1ギガになるようなケース。⾼度化と映るかもしれないが、⾼感度化によって研究のスピードは数百倍も変わってく世界。もはや全然違う研究のやり⽅になってくる。これはユーザーからしたらインクリメンタルな変化ではなく、ディスラプティブなこと。 その境界は曖昧。全く今まで存在しなかったプローブであるとか、量⼦計算などによって初めて切り拓かれる地平もあるので、どちらも⼤事だし、どちらかだけを優先すべきだみたいなものでは必ずしもない。
熊本:研究者の⽴場から⾒た場合、ほとんどの取組は連続性の中にある。⾶び抜けて新しい開発が進んだ成果が周知されると、連続的な取組がレトリックの中に隠れてしまう。少しのインプルーブが、⽤途先が変わるだけでイノベーションを引き起こすこともある。クライオ電顕のようなケースも、技術的には電⼦顕微鏡としてのコア技術に⼤きな変化はなく、冷やす技術とソフトウエア開発によるもの。
質疑7:OECDの提⾔には『データインフラとの連携』の項⽬が⼊っていて、これは⼤変重要な項⽬だと思っている。⽣成AI等の活⽤、クラウドサービスの提供とその活⽤というのが研究現場で⼤きなチャンス。ただ、サービスの提供者を⾒ると、Amazon、Microsoft、Googleといった海外が席巻をしていて、当然コストも⾼い。欧⽶ではその辺の共⽤や計算リソース、サービスの有効な活⽤はかなり進んでいるのか。もう⼀つ、クラウドサービスを海外ではなくて⽇本で提供できないのか。 データ科学⾯の先端のツールを⽇本の企業とかベンダーが提供するような可能性がないか。
永野:研究インフラは、ハードとデータ・ソフト、両⽅合わせて研究インフラ。データインフラを世界的にどういう議論で進めていこうとしているかは、まさに今、⾮常にホットなところ。国際的にも、論点を分けて整備・構築・運営していく必要があるとの考え⽅は共有されてきている。
さらに、データインフラといっても、全部共通にはならない。どのデータを扱うか、どういうフェーズにある研究開発を対象にするのか。これらによって全く違ってくる。利⽤の観点でも、データへのアクセスをどうするか、ユーザー認証をどうするか、研究セキュリティをどうするか。いずれも世界各国で論点になっている。
クラウドに関しては、安定で安全な箱を誰が提供するのかの話。⽇本のベンダーのクラウド環境の可能性を追求することも選択肢としてはあるだろう。ただし、これはあくまでも利⽤の観点で⾒ることが重要で、安定した安全な運⽤が必要になる研究現場からの⾒⽅がポイントになるのではないか。

最後に隅藏⽒は、「研究基盤、研究インフラの開発・実装、利⽤成果創出の循環の実現は、開発する産業側の政策、利⽤する科学技術政策の間でコンフリクトやトレードオフがあるのではないかと議論を始めた。まさにそれらを統合したところの政策、多様な視点をそれぞれが認識し、視野を広げてエコシステムを形成していくことが重要だ」と述べ、締めくくりました。
登壇者プロフィール
永野 智⼰(ながの としき)
科学技術振興機構・研究開発戦略センター(JST-CRDS)フェロー・総括ユニットリーダー/
⽂部科学省・マテリアル先端リサーチインフラPO
学習院⼤学理学部化学科卒、グロービス経営⼤学院経営学修⼠(MBA)。科学技術振興事業団2003年⼊社(現 科学技術振興機構JST)。2007年よりJST研究開発戦略センター(CRDS)フェロー、ナノテクノロジー・材料ユニットリーダー等を経て、2018年よりCRDS総括ユニットリーダー(現職)。同年、JST研究監。他、2015年より⽂部科学省技術参与として、マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)のPOやプロセスサイエンス構築事業のPOを兼任。専⾨はナノテクノロジー・材料、研究開発戦略、技術経営、異分野融合・技術プラットフォーム・イノベーションエコシステム形成論等。
熊本 明仁(くまもと あきひと)
⽂部科学省科学技術・学術政策局研究環境課 上席調査員
⽴命館⼤学⼤学院理⼯学研究科卒、博⼠(理学)。⽇本学術振興会特別研究員DC2。2011年より東京⼤学⼯学系研究科総合研究機構特任研究員、上席研究員を経て、2019年より⽂部科学省卓越研究員事業にて⽇本電⼦株式会社に⼊社。透過型電⼦顕微鏡を⽤いた材料研究を継続するとともに、2021年より同社経営戦略室にて東京⼤学との連携拠点の運営及び研究⽀援業務、2022年より同社の技術/オープンイノベーションマネジメント業務を兼務。2023年10⽉より⽂部科学省科学技術・学術政策局研究環境課上席調査員として研究基盤の強化に向けた政策⽴案・推進等に関する調査に従事。
隅藏 康⼀(すみくら こういち)
政策研究⼤学院⼤学(GRIPS)教授
東京⼤学⼤学院⼯学系研究科にて博⼠号(⼯学)取得後、同学先端科学技術研究センター客員助⼿、同センター助⼿、政策研究⼤学院⼤学助教授、同学准教授を経て、2016年より現職。専⾨分野は、知的財産政策、科学技術政策。2012年6⽉から2015年5⽉まで⽂部科学省科学技術政策研究所(現・科学技術・学術政策研究所(NISTEP))第2研究グループ総括主任研究官を兼任。2023年10⽉よりSciREX共進化実現プログラム(第Ⅲフェーズ)「研究⽀援の基盤構築(研究機関・研究設備・⼈材等)のための調査・分析」プロジェクト代表。
執筆:天元 志保(⼀般社団法⼈知識流動システム研究所 理事)