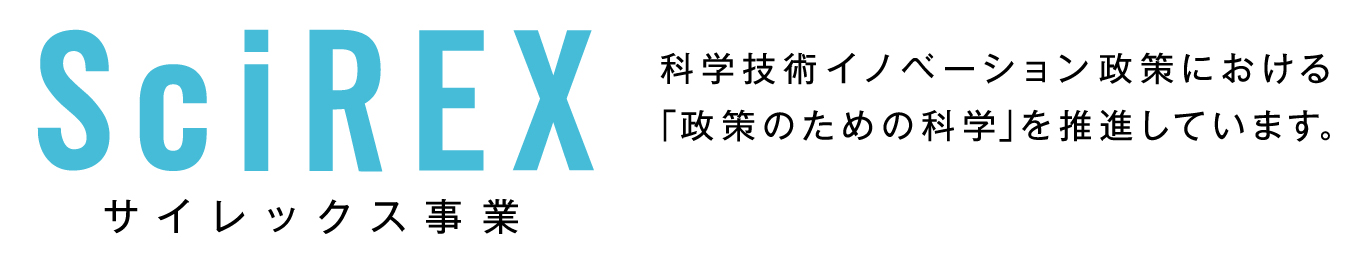第50回SciREXセミナー 開催報告⾰新と成⻑の源、
第50回SciREXセミナー 開催報告⾰新と成⻑の源、
⽇本における研究インフラの
エコシステム形成
ディスカッション:開発から調達・利⽤成果創出がサイクルするエコシステム形成へ向けて共⽤システムと市場拡⼤の関係性
⽇本の研究インフラの発展には、永野⽒が報告したように国際競争の視点を踏まえた包括的な戦略の策定と実⾏が求められています。ここで⽣まれる更なる課題について、参加者からの質疑も交えながらディスカッションを通じて深めました。

まず、研究機器の共⽤促進と市場拡⼤の関係について、ファシリテータの隅藏⽒から「研究費の使⽤の効率化と設備へのアクセシビリティーの向上のために共同利⽤(以下、「共⽤」)が促進されるほど、市場が縮⼩するのではないか」という問題提起がなされました。これに対して永野⽒は、マクロな視点ではそんなことはなく、機器産業と共⽤は決してトレードオフではないと回答。「世界の研究機器市場は近年成⻑を続けており、 研究者・利⽤者のニーズは拡⼤傾向にある。なぜ拡⼤しているのかを考えたときに、次なるサイエンスの地平をどこで広げていくのかというとき、新しい研究課題に挑みたい⼈が集まる場と、新しいテクノロジーに対しこんな使い⽅ができると提⽰できる産業界と技術者を擁する、そういう場がおそらく次の共⽤拠点の姿になる」と述べました。

熊本⽒は、現代の先端研究における複合的な機器使⽤と、それを踏まえて複数の企業が協働開発に取り組むケースが増えていることを強調。その結果、オープンイノベーションの場が重要視されているとし、「企業側は作ったものをいち早く使ってもらいフィードバックを得たいが、共⽤によってその取組が加速化し、装置が改良される」と述べました。また、「最先端・最⾼性能でも、使い勝⼿がいいとは限らない。 製品として市場に供給していくには改良が必要で、その観点で異なる視点でさまざまな研究課題を持つ⽅々が使⽤できる共⽤が不可⽋」であると説明しました。
国際競争⼒強化に向けた視点
次に、隅藏⽒は、⽇本の研究機器の国際競争⼒を⾼め、⽇本のものづくりを活⽤して、海外展開していくことを考えた場合には、やはり研究の分野の中でデファクト・スタンダード獲得が重要と指摘。「研究成果⾃体が⼀種の宣伝となって、デファクト・スタンダードになっていくといったサイクルが考えられる。それも含めて⽇本の研究機器業界、あるいはそれに関連するアカデミアとしては、 国際的な競争⼒を⾼めるためにどういったことをしていくことが必要か」と問いかけました。

これに対して永野⽒は、⼀つの観点として重要としながらも、「ある種の戦術論。もう少し⼤きく戦略として⾒たときにより重要なのは、未開のサイエンスの広がり」と答え、新しいテクノロジーがあればそこに挑んでいけるということをテクノロジーサイドが⽰していくべきと述べました。これに熊本⽒も、「新たな課題を持つユーザーだけでなく、技術を作っていく側も交えて、両者が次のイノベーションの源泉を⾒据えることは必要」と賛同しました。
また、永野⽒は、⽇本の研究現場が直⾯する構造的な問題として、海外の機器開発国と⽐べて導⼊が遅れ、最先端の研究競争で常に不利な⽴場に置かれることに警鐘を鳴らしました。「⽇本の開発⼒を上げて、⽇本の研究現場が世界の研究競争の最先端から乗り遅れていかない状況を」と強調しました。
諸外国におけるイノベーション調達制度の戦略的活⽤
諸外国のイノベーション調達制度の戦略的活⽤について、永野⽒は、研究環境は研究⼒と直結しており、劣後する要因の⼀つとしてイノベーション調達制度の有無があると述べました。「欧州各国、⽶国、韓国では、イノベーション促進型の調達制度を法体系から整備し、制度化。国⽴研究機関や⼤学等への戦略的な先端技術導⼊を進めている」とし、⽇本では研究⼒の観点で⾒たときのやり⽅としては制度設計されていないと説明しました。
特に韓国では、欧⽶の制度を学び⾃国流にアレンジした結果、現在は世界で最も進んだイノベーション調達制度を持つに⾄ったと評価。「欧⽶韓の制度設計を分析し、⽇本に合うやり⽅としてインストールするにはどうしたらいいかを考えてみるのがよい」と述べました。
エコシステムを介して⽣じる作⽤の戦略的マネジメント