RISTEXプロジェクト3病床の減床と都市空間の再編による健康イノベーション

津田塾大学総合政策学部 教授
病院の立地を理論的に提案するものの・・
「平成の大合併」により、2005-06年をピークに多くの市区町村が合併しました。その後、日本の人口は減少に転じ、超高齢化も進んでいます。このような社会の変化は、病院のあり方にも大きな影響を与えています。
伊藤さんは、2013-15年度に日本学術振興会のプロジェクト(課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業(実社会対応プログラム)「病院を中心とする街づくり まちなか集積医療の提言」)において、「人口や人口密度の変動」と「病院の立地や機能の変化」の関係を、データに基づいて解析しました。特に、人口10-30万人程度の15の中規模都市を対象として、医療の中核となる病院の統合の影響を、データに基づいて詳しく調べました。その結果、例えば、病院統合によって、救急搬送に要する平均時間が一部長くなったとしても、一箇所に多くの医療スタッフがかかわることで、搬送傷病者の病院受入不可の頻度が減らせる、といった結果が得られました。つまり、病院を街の中の便利な場所にまとめれば、医療者にとっても市民にとってもアクセスのよい医療が実現できるというエビデンスが得られたのです。
「このプロジェクトは政策提言が主眼ではありませんでしたが、いくつかの自治体や病院の方々に、統合にメリットがあることをご説明しました。しかし、いくら理論的なエビデンスがあっても、病院の統合は人が行うことです。様々な立場のステークホルダーが関わっており、それぞれに思いがあるため、話がそう簡単には進まないということを痛感しました。そこで、私たちの提案が“どうして現場に届かないのか”という理由と、“どうしたら届くのか”という方法をいろいろ考えた末、今回のプロジェクトを計画したのです」。
持続可能な都市があってこその持続可能な医療
今回のプロジェクト名に入っている「病床の減床」は、国の政策でもあります。「疾患ごとの入院データを解析すると、ほとんどの疾患で、急性期の医療行為に相当する入院日数は4日程度で、残りの入院日数は経過観察のために取られていることがわかります。長い入院は、患者さんの健康状態の低下、医療従事者の負担増加、社会保障費の財政圧迫につながり、全体的には三重苦のような状態です。しかし、現場では、病床を減らすことは、事業規模の縮小や収益の減少に直結するわけですので、減床政策への抵抗が根強くあります」。
つまり、客観的に見れば「減らしたほうが良い」と思っても、当事者にしてみれば「減らす動機が持てない」ことが、政策が現場に届かない理由だという考えに至ったのです。このため、伊藤さんは「誰もが合意できるゴール」を掲げることにしました。そのゴールは、「持続可能な地域があってこその、持続可能な医療」という考えです。このゴールは、都市空間づくりの中で病院のあり方を考えようというもので、医療の需給だけに囚われてしまった先行プロジェクトの反省に基づいています。
「このゴールに到達するには、医療現場にとってベネフィットとなり、患者さんにとっても望ましいサービスが得られるようにビジネスモデルの転換を図る必要があります。今回のプロジェクトでは、データに基づいて、5-10年先の都市と病院の姿を予想しますが、その予想に対応するための都市の変化は、必ずしも医療サービスの変化だけではなく、他の選択肢もあると思います。都市のスタイルに応じて、比較可能な複数の案が出ることのほうが自然だと思います」。
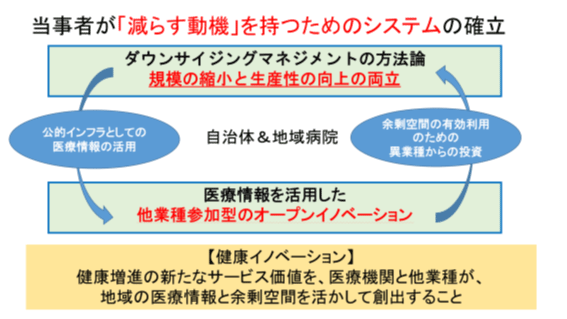
5-10年先の都市の様子を予想するには、例えば、厚生労働省による人口動態統計のデータを用います。ある地域での出生数や婚姻、社会的な人口移動、在宅での看取りや病院での看取りの数などをもとに、都市空間の構成を捉えるのに必要な基礎データをつくっていきます。また、病院が保有している治療の情報から、地域の医療ニーズを掴むことも重要です。「両者をつなぐことで都市と病院のあり方の予想が可能になりますが、現状ではつながれていないのが問題です。データを収集し、つなぐ作業は地味なものですが、それを私たちがやることに意義があり、得られた結果が基礎となるので、しっかり取り組んでいきます」。
また、データさえあれば良いというものではなく、合意に至るまでには様々なプロセスが必要で、現状ではそれらの方法論が標準化されているわけではありません。各自治体や病院にとってみれば、医療機能を大きく転換するような経験がこれまでにないほうが一般的です。そこで、伊藤さんたちは、全国各地で地域医療の機能分担が成功している事例、そして、そうではない事例を調査し、その結果をもとに効率的な意思決定のプロセスを確立することを目指しています。「他の地域の事例というのは、単に真似ればよいというものではなく、その背後にある方法論を詰めることが先決だと思います」。
発想の転換で病院に新たな風を吹き込む
減床を促す病院のビジネスモデルとして、伊藤さんたちは2つのアイデアをもっています。
「1つは、減床であいたスペースを他のビジネスで利用することです。医療関係者は、病院は病気を治すところだという概念にとらわれがちですが、それを取り払うような選択肢を提供できたらと考えています。例えば、病院も生活の場として、一部を居住空間としたり、温泉、映画館、イベントスペースなどを設けたりしてもいいと思うのです。医療法人がそうした施設を直営することはできませんが、別の企業と協力すれば可能です。すでに、カロリーを抑えた食事を提供する食堂や、アメニティーとしてのバーが病院に設けられている例はあります。そうした事例を調査して、私たちが対象とする病院に対しても、地域と病院の実情に合った空間の利用法を提案できればと考えています」。
もう一つは、病院が保有する医療情報を、ビジネスに利用することです。「病院からデータをそのまま提供していただくことには、個人情報の問題などの難しさがあります。ですので病院との信頼関係を前提に、病院や地域にとってメリットとなる提案を目指し、地域の医療が見えるデータに加工することが必要です。そして、こうした情報は、個人情報が付随していなくてもビジネスへの利用が可能です。例えば、独居で外出しにくい高齢者が多く住んでいるといったことがわかれば、見守りサービスや食品の宅配などのビジネスの参入が考えられるといった具合です」。

伊藤さんたちは、先行プロジェクトで調査した自治体の中から3、4ヵ所を選び、モデルケースとして、さらにデータ収集、事例調査を行うとともに、街づくりのプロセスに関わる体制を整えていく計画です。「プロジェクトのメンバーには、三重、山形、奈良、新潟などで、地元の自治体や病院と密接なつながりをもつ研究者も入っているので、そのネットワークも生かして、現場のステークホルダーの間に入ってコーディネートを行えればと考えています」。その後、対象を広げ、3年間で10ヵ所程度を調査し、提案を行う予定です。
今回のプロジェクトで、研究者である伊藤さんが「現場」に踏み込んでいくのはなぜでしょうか?「経済学の分野では、データを分析して学術論文で問題点を指摘しても、それによって政策が変わるには長い時間がかかります。また、純粋な『科学』とは違って、学術的な指摘だけでは現場には届かないことも多いのです。ですから、このプロジェクトでは、研究から現場での提案までにかかる時間を少しでも短くしたい。そのために、逆説的なようですが、研究者らしく地味なデータをほりおこし、そして現場に直接提案していくつもりです」。
